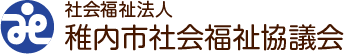福祉委員の歴史
「福祉委員制度」は、平成5年3月より市内各町内会へ設置をお願いし、本年度で32年目となりました。令和7年4月現在、59町内会(65町内会)に設置されており、226名の福祉委員が各町内会において活躍されております。
福祉委員とは?
「稚内に住んでいて良かった!」「安心して暮らせる町内会」と言われるような地域づくりをめざし、生活課題や福祉課題を早期に発見することが福祉委員の大きな役目です。
- 自分の町内会の人に声掛けをすることにより、心が通い、お互い助け合って暮らしていける形をつくる。
- ひとり暮らしの方等の安否を気遣ってあげる。(新聞が溜まっている、夕方になっても電気が点かない、最近姿が見えない等)
- いろいろな手伝いをしてあげる。(もし必要ならば洗濯、買い物、縫い物、炊事を手伝う、買い物付き添い、除雪の手伝い、ゴミ捨て等)
- 何か問題を発見したら‥‥すぐ地域の民生委員児童委員や町内会役員等へ連絡すること。
- 民生委員児童委員からの協力依頼には積極的に応えていく。
福祉委員活動例
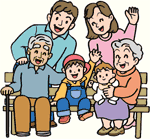 勉強会の開催(福祉委員が勉強をする、町内会で勉強会を開催する)
勉強会の開催(福祉委員が勉強をする、町内会で勉強会を開催する)- 福祉委員のPR訪問、回覧板の活用
- 福祉マップの作成(高齢者・障害者の居住地図の作成)
- 声掛け・安否確認
- ふれあいランチ事業・いきいきサロンの開催
- 除雪活動(町内に除雪隊を組織しての活動)